審査員メッセージ

モニカ・ビンチク(米国)
メトロポリタン美術館東洋美術部日本工芸学芸員
メトロポリタン美術館東洋美術部日本工芸学芸員。彼女は美術館において数多くの展覧会を企画し、その中には「着物スタイル:ジョン・C・ウェバーコレクション」(2022)、「京都―芸術的創造力の都」(2019)、「日本の竹工芸:アビー・コレクション」(2017)、「日本美術の発見:アメリカ人コレクターとメトロポリタン美術館」(2015)がある。日本の工芸と収集歴に関して多数執筆しており、近年では『着物スタイル:江戸の伝統から現代のデザインへ』(メトロポリタン美術館、2022)、『源氏物語:千年の時めき』(メトロポリタン美術館、2019)を手がけている。
メッセージ
技術の熟練度、素材の良さ、高いデザイン感覚といった特別な感性は、工芸の作り手を際立たせる。世界規模での技術知識の流通、新素材の可能性、伝統的手法の再発見など、工芸は新たな課題に直面している。そのキーワードのひとつが「ネットワーキング」であり、芸術領域や社会的実践、ライフスタイルの変化、メディアの存在など、さまざまなつながりがますます創作活動に影響を及ぼしている。世界各地から応募される、刺激的で新鮮な工芸の作品を楽しみにしている。

チョ・ヘヨン(韓国)
韓国アート・アンド・デザイン協会 会長
1969年韓国ソウル市生まれ。英国・ブリストルの西イングランド大学アート・デザイン校にて陶磁の優等学位を取得。ソウルの梨花女子大学校にて陶磁の修士号を取得、また同大学にて美学・ビジュアルアーツの博士課程を修了した。「京畿道国際陶磁ビエンナーレ2013」では国際委員、2016年「韓国の現代陶芸」(ベルナルド財団、リモージュ、フランス)のゲストキュレーター、2015年清州国際工芸ビエンナーレのアートディレクター、2017-2018年「韓国の現代陶芸」(ヴィクトリア & アルバート美術館、英国)のゲストキュレーター、ミラノデザインウィークの「伝統と革新:韓国工芸展2017」、韓国工芸デザイン文化振興院事務局長、「統営国際トリエンナーレ2022」のキュレーターを務めた。メトロポリタン美術館、ヴィクトリア&アルバート美術館、リウム美術館など、世界各地の著名な施設にて数多くの展覧会を企画し、講演も行っている。韓国ロエベ財団クラフトプライズのコミッショナーを務めるほか、専門家委員会の委員も務める。
メッセージ
金沢・世界工芸トリエンナーレは日本の工芸の発展に確かに貢献している。その役割はかけがえのないものであり、審査員の一員である私はこの重要なイベントに携わることを心より名誉に思う。本トリエンナーレに応募された創造的な作品は、現代における工芸の全体的な発展を長きに渡って例証している。古代の技術から新しいテクノロジーまで、本トリエンナーレは時代の流れと並行している。そしてそのテーマは、社会的、経済的、芸術的な転換期の必要性を反映している。

林曼麗(台湾)
国立台北教育大学 名誉教授、北師美術館 創設者・総合プロデューサー、元国立故宮博物院 院長
東京大学大学院教育学研究科博士。国立台北教育大学名誉教授、北師美術館創設者・総合プロデューサー。過去に、台北市立美術館館長、国立故宮博物院院長、財団法人国家文化芸術基金会理事長などを務める。台湾美術史の研究ならびにその教育活動、国際的な展覧会のキュレーション、企業とのタイアップ事業のディレクションなどに、長年携わっている。2011年に国立台北教育大学にて北師美術館を立ち上げ、新しいミュージアム像の構想を提示。同美術館で、実験的かつ分野横断的な展示や舞台芸術公演を多数企画しているほか、地域に開かれた場づくりにも力を入れている。長年に亘る日台間の文化・学術交流及び相互理解の促進に尽力し、2023年秋の外国人叙勲で旭日中綬章を受章された。
メッセージ
工芸とは人とモノを緊密に結んできた緒であり、モノの働きによって文明がつくられ、人類の文化が躍進した。フランスの社会人類学者のレヴィ=ストロースが指摘したように、技芸こそ宇宙のなかで自分らしくいられる場所なのである。工芸はこれまでも、人と他者、人と自然、人と環境を引き合わせ、己との対話を促し、あらゆる相関関係のなかで、なくてはならない大切な役割を担ってきた。伝統技能と現代のモノづくりを、クロスオーバーさせて深化する金沢・世界工芸トリエンナーレは、枠に囚われない、想像を越えた創作表現の可能性を、この先も示し続けてくれるだろう。

唐澤昌宏
国立工芸館長
1964年愛知県名古屋市生まれ。愛知県立芸術大学大学院美術研究科修了。愛知県陶磁資料館(現、愛知県陶磁美術館)学芸員を経て、2003年に東京国立近代美術館主任研究員。2010年に工芸課長。2020年より現職。2018年第39回小山冨士夫記念賞(褒賞)受賞。専門は近・現代工芸史。日本陶磁協会賞選考委員。著書:『窯別ガイド日本のやきもの 瀬戸』(淡交社)。共著:『日本やきもの史』(美術出版社)、『やきものを知る12のステップ』(淡交社)など。近年の主な展覧会の企画・監修:「近代工芸と茶の湯のうつわ―四季のしつらい―」(2021年)、「未来へつなぐ陶芸 伝統工芸のチカラ展」(2022年)、「『ひとがた』をめぐる造形」(2022年)、「ポケモン×工芸展 美とわざの大発見」(2023年)、「卒寿記念 人間国宝 鈴木藏の志野展」(2024年)など。
メッセージ
工芸という領域を、広義的に捉えるのか、あるいは狭義的に捉えるのか、それはつくり手しだいだ。ただ言えることは、どんなに素晴らしいコンセプトやアイディアがあろうとも、素材に対する深い理解と確かな技が伴わなければイメージを形にすることはできない。その両立とともに、つくり手が考える新しい価値観や独特の世界観が盛り込まれた作品が示される場となることを期待したい。

青柳正規
石川県立美術館長、多摩美術大学 理事長、元文化庁長官
1944年大連生まれ。古代ローマ美術・考古学を専攻。東京大学文学部部長、国立西洋美術館館長、文化庁長官などを務め、現在、東京大学名誉教授、日本学士院会員、学校法人多摩美術大学理事長、山梨県立美術館館長、奈良県立橿原考古学研究所所長、石川県立美術館館長他。50年に亘りイタリアの古代ローマの遺跡発掘に携わる。国内では、日本放送協会放送文化賞(2011年)などを受賞、紫綬褒章(2006年)、瑞宝重光章(2017年)受章、文化功労者顕彰(2021年)。海外ではいずれもイタリア にて、Sebetia Ter国際賞(2008年)、Torquato Tasso国際賞(2017年)、Amedeo Maiuri 国際考古学賞(2019年)などを受賞、イタリア共和国功績正騎士勲章(2002年)受章。著書は、『皇帝たちの都ローマ』、『ローマ帝国』、『文化立国論』、『人類文明の黎明と暮れ方』他。
メッセージ
日本が自信を持って世界に誇ることのできる伝統工芸には、日本の歴史、文化、気候風土だけでなく日本人の感性や美意識が凝縮されている。日本各地で様々な伝統工芸品がつくられ使用されている中で、特に北陸地方はその伝統がもっとも濃密だと言えるだろう。そこに住む人々の伝統工芸に対する愛着が深く、それゆえに伝統工芸を見る目も肥えている。金沢・世界工芸トリエンナーレはそのような地域において伝統工芸に更なる輝きの光を浴びせる。
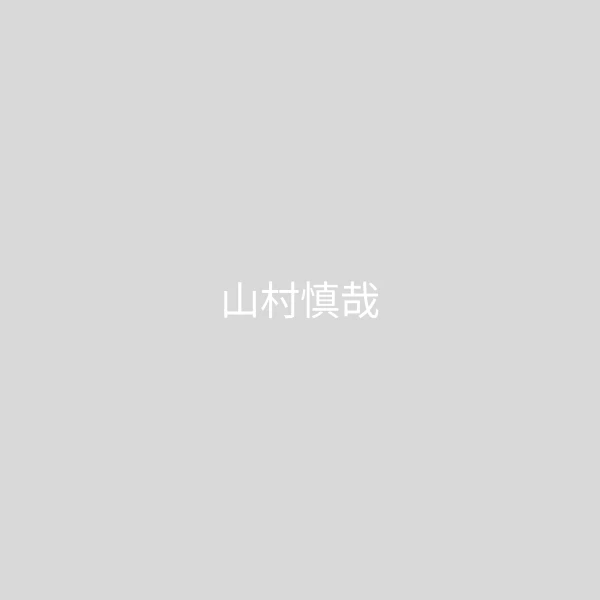
山村慎哉
金沢美術工芸大学 学長
1960年東京都調布市生まれ。1986年金沢美術工芸大学大学院修了後、個展や国内外の企画展などで活動し1992年より金沢美術工芸大学の教員として赴任。精緻で凝縮された漆芸の加飾技法を中心とした制作研究を展開。個展:髙島屋、三春堂ギャラリー、ギャラリー点、一穂堂、SILVER SHELL、エキシビションスペース他。企画展:「RIVALUE NIPPON PROJECT展」(パナソニック汐留ミュージアム)、「NY工芸未来派」(MAD)、「清州ビエンナーレ講演会」(韓国)、「国際アジア漆シンポジウム・展覧会」(バッファロー大学)、「工芸未来派」(金沢21世紀美術館)他。作品収蔵先:ヴィクトリア・アルバート美術館、スコットランド王立美術館、ロサンゼルスカウンティーミュージアム、シアトル美術館、サンフランシスコ・アジア美術館、アシュモレアン美術館、スミソニアン博術館アジアギャラリー、ウォルターズ美術館、金沢21世紀美術館、広島市立大学芸術資料館、金沢卯辰山工芸工房、金沢市立安江金箔工芸館他。
メッセージ
サステナブルな未来とは、人間と自然が共存し、次世代に豊かな環境と社会を継承する未来を意味する。工芸もまた、場にある素材や時代の技術を駆使し、地域の文化や伝統に根ざしながらも、時代や環境に応じた新しい美と実用性を提供してきた。金沢・世界工芸トリエンナーレでは、伝統と革新が交わり、多様な価値観が尊重される場を創出する。国境や人種を越えた工芸の魅力を共有し、未来へと受け継ぐ新たな文化交流の場となることを心から願っている。

中川衛
金工作家、重要無形文化財「彫金」保持者
1947年石川県金沢市生まれ。彫金の技法のひとつで、石川県に伝わる伝統工芸「加賀象嵌」の第一人者。日本伝統工芸展「日本伝統工芸会保持者賞」受賞(2001年、2003年)。MOA美術館第13回岡田茂吉工芸部門大賞受賞(2002年)。重要無形文化財「彫金」保持者(人間国宝)に認定(2004年)。メトロポリタン美術館(2008年、2020年)、大英博物館(2010年)に作品が収蔵される。紫綬褒章(2009年)、瑞宝中綬章(2018年)受章。現在は精力的に作品制作に励むほか、金沢職人大学校、金沢卯辰山工芸工房で指導をするなどして後進の育成にも力を注いでいる。金沢美術工芸大学名誉教授。
メッセージ
人々の物への価値観、生活様式の多様性など変化してきている。それに伴い工芸の範囲も拡がり、より芸術性豊かなものを求められる。本トリエンナーレでは新感覚な作風、創造性豊かな作品、若い方の活力ある作品が各国から多く提案され、見る方、作る方々、あるいは工芸業界に今後の工芸作品の方向性の一つの提示となれば幸いと思っている。大いに期待している。

十一代 大樋長左衛門(年雄)
日本藝術院会員、美術家
1958年、金沢市に十代大樋長左衛門の長男として生まれる。1984年、ボストン大学大学院修士課程修了(M.F.A.)。美術家としての活動は多岐にわたり、シンガポール・UOB 銀行ロビーでの4mにわたる金属アートワーク、イタリア・ミラノサローネでの家具デザイン、インテリアやボトルなどのデザイン、アイウェアではグッドデザイン賞を受賞している。作品は、大英博物館(イギリス)、カウンティー美術館(米国・ロサンゼルス)など世界各国に所蔵され、第54回日本現代工芸美術展 「内閣総理大臣賞」受賞、第8回日展 最高賞「文部科学大臣賞」受賞、ハンガリー国家勲章叙勲、恩賜賞・日本藝術院賞受賞、令和6年度外務大臣表彰など受賞多数。
メッセージ
人はAIから学び、バーチャル空間によって自然を感じる時代が到来している。ではこれから「工芸」は、どのように変貌しなければならないのだろうか。人が創り出した「工芸」は、これまで世界に何が起ころうとも、人の心に寄り添ってきた。素材やそれぞれの文化を再考し、未来的な回答を期待している。